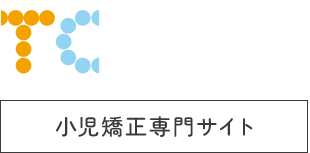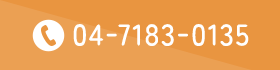子どもの歯並びが悪い理由
お子さまの歯並びが乱れる原因はさまざまですが、なかにはご家庭では気づきにくいものもあります。できるだけ早めに歯科医院のチェックを受けておくようにしましょう。
ここでは、代表的な3つの要因をご紹介します。
遺伝によるもの
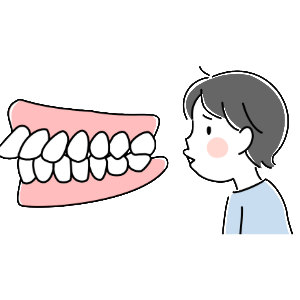 出っ歯や受け口などは、骨格や歯の大きさ・顎の形といった遺伝的な要素が影響することがあります。
出っ歯や受け口などは、骨格や歯の大きさ・顎の形といった遺伝的な要素が影響することがあります。
また、通常より歯が多い「過剰歯」や乳歯がくっついて生える「癒合歯」といった先天的な歯の異常によって、歯並びが乱れるケースもあります。
習慣や癖によるもの
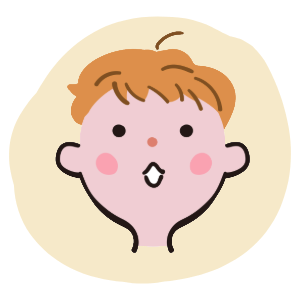 舌で前歯を押しだす癖や、頬杖、指しゃぶり、爪を噛む癖などのちょっとした習慣が歯並びや顎の発育に影響を及ぼすこともあります。
舌で前歯を押しだす癖や、頬杖、指しゃぶり、爪を噛む癖などのちょっとした習慣が歯並びや顎の発育に影響を及ぼすこともあります。
また、いつもお口を開けっぱなしにしている「お口ポカン」の状態も注意が必要です。これはお口まわりの筋力が低下しているサインで、出っ歯や顎の発育不良、かみ合わせのズレにつながることもあります。
乳歯のむし歯の放置によるもの
 「いずれ抜けるから大丈夫」と思われがちな乳歯ですが、乳歯には永久歯を正しい位置に導く大切な役割を持っています。
「いずれ抜けるから大丈夫」と思われがちな乳歯ですが、乳歯には永久歯を正しい位置に導く大切な役割を持っています。
むし歯の進行によって本来よりも早く乳歯が抜けてしまうと、両隣の歯がその空いたスペースに倒れてきてしまい、永久歯が正しく生えるスペースがなくなってしまうことがあります。その結果として、歯並びがガタガタになってしまう可能性があります。
子どもの歯並びを予防しないとどうなる…?
歯並びの乱れは、見た目への影響だけではなく、日常生活や健康面にもさまざまな悪影響を及ぼすおそれがあります。
ここでは、代表的な4つの影響をご紹介します。
むし歯や歯周病になりやすくなる
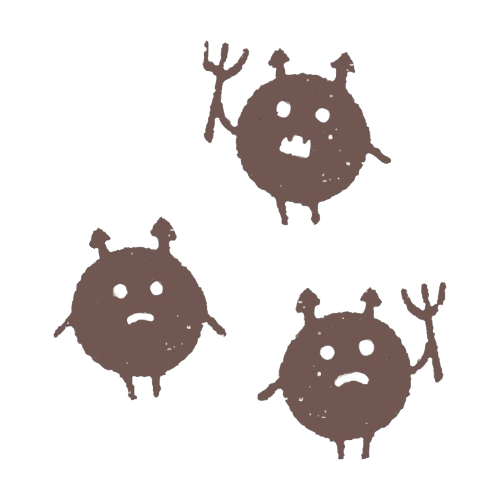 歯並びが乱れ、ガタガタしていると、歯ブラシが届きにくい箇所が多くなり、磨き残しが生じやすくなります。
歯並びが乱れ、ガタガタしていると、歯ブラシが届きにくい箇所が多くなり、磨き残しが生じやすくなります。
その結果、むし歯菌や歯周病菌が繁殖やすくなり、むし歯や歯周病リスクを高めてしまいます。
姿勢や体のバランスにも影響
かみ合わせがズレていると、無意識のうちに体のバランスを取ろうとして首や肩、背中などに過度な負担がかかることがあります。
その結果、猫背や左右の肩の高さの違いなどが生じ、姿勢が悪くなりやすいです。また、しっかり噛めないことで全身に力が入りにくく、スポーツのパフォーマンスにも影響が出ることがあります。
発音が不明瞭になる
 歯並びの乱れによって歯の隙間から空気が漏れたり、舌の動きが制限されたりすることで、サ行やタ行などの発音が不明瞭になることがあります。
歯並びの乱れによって歯の隙間から空気が漏れたり、舌の動きが制限されたりすることで、サ行やタ行などの発音が不明瞭になることがあります。
発音が不明瞭になると人とのコミュニケーションにも支障が出るおそれもあります。
お口が乾きやすくなる(ドライマウス)
上の歯が前に出ている「出っ歯」や上下の歯がしっかり閉じない「開咬(オープンバイト)」だと、口を閉じにくくなります。
常にお口が開いていると、お口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなります。お口の乾燥はむし歯や口臭、風邪などの原因にもつながるおそれがあります。
よくある子どもの歯並びと対処法
前歯にすき間がある(すきっ歯)
 すきっ歯は、お子さまの歯の生えかわり時期によく見られます。ほとんどの場合は、永久歯が生えそろうことで自然にすき間が埋まっていきます。
すきっ歯は、お子さまの歯の生えかわり時期によく見られます。ほとんどの場合は、永久歯が生えそろうことで自然にすき間が埋まっていきます。
ただし、犬歯(前から3番目の歯)が生えたあともすき間が残っている場合には、歯科医院でチェックを受けることをおすすめします。すきっ歯は、食べ物が詰まりやすく、むし歯や歯ぐきのトラブルが生じやすくなるおそれがあります。
歯がデコボコに並んでいる(叢生)
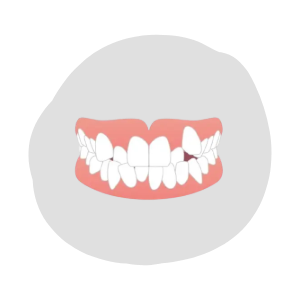 叢生(そうせい)は、日本人に多く見られる歯並びの乱れです。歯のサイズや本数に対して、顎が小さい場合に歯が並びきらず、重なり合って生えてしまいます。
叢生(そうせい)は、日本人に多く見られる歯並びの乱れです。歯のサイズや本数に対して、顎が小さい場合に歯が並びきらず、重なり合って生えてしまいます。
生えかわりの時期に合わせて、顎をゆっくり拡大したり、マウスピースを使って歯の位置を整えたりする方法があります。早めに治療を開始することで、将来的な抜歯のリスクを減らせる可能性を高めます。
前歯が前に出ている(出っ歯)
 出っ歯の原因には、骨格的なものと、指しゃぶりや舌で前歯を押す癖などがあります。骨格が関係している場合は、顎の成長が活発なうちに治療を始めると、自然なかたちで整えやすくなり、治療の負担や費用を抑えられることがあります。
出っ歯の原因には、骨格的なものと、指しゃぶりや舌で前歯を押す癖などがあります。骨格が関係している場合は、顎の成長が活発なうちに治療を始めると、自然なかたちで整えやすくなり、治療の負担や費用を抑えられることがあります。
癖が原因の場合は、すぐに矯正が必要とは限りませんが、舌の使い方やお口まわりの筋トレーニングなどを取り入れていくことで、歯並びの改善や安定につながります。