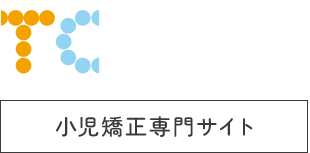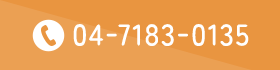- 子どものマウスピース矯正とは?
- 成長期にこそ始めたいマウスピース矯正
- 当院で使用されるマウスピース装置の種類
- マウスピース矯正のメリットと注意点
- お子さまのマウスピース矯正を成功させるためのポイント
- お子さまのマウスピース矯正について、よくあるご不安や疑問にお答えしています。
子どものマウスピース矯正とは?
マウスピース矯正の目的
マウスピース矯正には大きく分けて2つの目的があります。
- お口まわりの悪い癖(舌の位置・口呼吸・嚥下など)にアプローチし、歯列や顎の正しい発育を促す治療
- すでに生えそろった永久歯の歯並びを整える治療
年齢や歯の状態によって、使用する装置や治療内容が異なるため、お子さまに合った最適な治療計画を立てることが重要です。
成長期に合わせたメリット
顎の成長が活発な時期に治療を行うことで、お子さま自身の成長力を利用して歯並びを整えることができます。
また、ワイヤー矯正よりも装置の違和感が少なく、通院や日常生活のストレスを軽減できるのも大きなメリットです。
成長期にこそ始めたいマウスピース矯正
 成長期のお子さまには、顎の骨の発育やお口まわりの筋肉の動きに合わせて歯並びを整えられるマウスピース矯正がおすすめです。
成長期のお子さまには、顎の骨の発育やお口まわりの筋肉の動きに合わせて歯並びを整えられるマウスピース矯正がおすすめです。
当院では、顎の成長が活発な時期のお子さまには、お口まわりの悪い癖(舌の位置・口呼吸・嚥下など)にアプローチして歯列や顎の正しい発育を促すマイオブレースを使用しています。
その後のリカバリーや第二期治療では、乳歯が残っている時期でも使用できるシュアスマイルを用い、顎の正しい発育を促しながら、舌の癖や口呼吸など歯並びに影響する習慣も改善していきます。
これにより、永久歯が生えそろった後もきれいな歯並びを安定して保ちやすくなります。顎の骨の成長には個人差がありますが、成長期の早めの段階で取り入れることで、より効果的に歯並びを整えることが可能です。
気になることがあれば、早めに歯科医師へご相談ください。
当院で使用されるマウスピース装置の種類
マイオブレース

成長期の子どもを対象とした「筋機能矯正装置」で、歯並びの乱れを引き起こす原因(口呼吸・舌の癖・姿勢など)にアプローチするのが特徴です。
取り外し可能なマウスピースを毎日一定時間装着し、あわせて呼吸や舌の使い方を改善するトレーニングを行います。
歯を抜かずに、成長を促しながら歯列を整えることが目的です。
特徴
- 成長期のお子さま向けの筋機能矯正装置
- 歯並びの乱れの「原因」にアプローチ(口呼吸・舌癖・姿勢など)
- 取り外し可能なマウスピース型装置
- 日中1〜2時間+就寝時の装着が基本
- 呼吸・舌のトレーニング(MFT)と併用して行う
- 顎の正常な発育を促し、歯を抜かずに歯並びを整える
シュアスマイル(第二期治療)

永久歯が生え揃ってから行う、二期治療に適したマウスピース型矯正装置です。
精密な3Dシミュレーションに基づいたカスタム設計で、必要な歯の動きを的確に実現できます。
透明な素材で目立ちにくく、快適な装着感も魅力です。ワイヤー矯正に比べて痛みが少なく、日常生活への影響も抑えられます。
特徴
- 永久歯列完成後の二期治療で使用
- 透明で目立ちにくいマウスピース型矯正装置
- 3Dシミュレーションに基づいた高精度な治療計画
- ワイヤー矯正よりも痛みが少なく快適
- 自分で取り外しができ、食事や歯磨きがしやすい
- 必要な歯の移動を効率的に行うことが可能
マウスピース矯正のメリットと注意点
見た目のメリット
 シュアスマイルなどのマウスピース矯正は装置が透明で、従来のワイヤー矯正に比べて目立ちにくいことが大きな特長です。マイオブレースも目立ちにくいデザインで作られており、日中の装着時間は1~2時間程度と短いため、学校や外出時には装着の必要がありません。そのため、見た目を気にすることなく治療を続けることができます。
シュアスマイルなどのマウスピース矯正は装置が透明で、従来のワイヤー矯正に比べて目立ちにくいことが大きな特長です。マイオブレースも目立ちにくいデザインで作られており、日中の装着時間は1~2時間程度と短いため、学校や外出時には装着の必要がありません。そのため、見た目を気にすることなく治療を続けることができます。
こうした特徴により、装着中の見た目に対するストレスを抑えられ、学校生活や写真撮影、日常の対人関係においても安心して治療を進められます。特に思春期のお子さまにとっては、周囲の目を気にせずに取り組めることが、モチベーション維持にもつながる大きなメリットとなります。
生活面でのメリット
 マウスピース矯正は食事の際に装置を取り外せるため、食べ物の制限がありません。
マウスピース矯正は食事の際に装置を取り外せるため、食べ物の制限がありません。
また、装置を外して歯磨きができるので、従来のワイヤー矯正よりも清掃性が高く、むし歯や歯周病のリスクを抑えることができます。
さらに、運動やスポーツの際も装置を外して安全に楽しめ、楽器の演奏時にも口元の違和感が少ないため、演奏への影響がほとんどありません。これらの点から、矯正治療中でもお子さまが普段通り快適に生活を送ることができます。
治療上のメリット
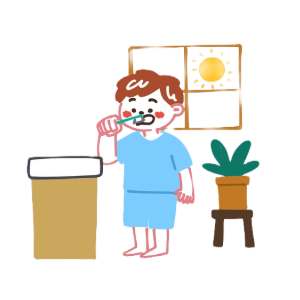 マウスピース矯正は強い力をかけずに少しずつ歯を動かすため、痛みが比較的少ない治療方法です。
マウスピース矯正は強い力をかけずに少しずつ歯を動かすため、痛みが比較的少ない治療方法です。
成長期のお子さまの発育を活かして効率的に歯並びを整えられるのも特徴で、顎の正しい発育をサポートすることで、より自然で安定した歯並びが期待できます。
さらに、装置は取り外しができるため清掃性が高く、むし歯や歯周病のリスクを軽減できます。通院も月1回程度で済むことが多いため、保護者の方の負担も少なく、早めに治療を始めることで将来的に抜歯を回避できる可能性も高まります。
注意点
装着時間を守る必要がある
取り外せるのがマウスピース矯正のメリットですが、その分「きちんと決まった時間装着すること」がとても大切です。推奨される装着時間を守らないと、効果が十分に出なかったり、治療が長引くことがあります。
ご家庭での管理・サポートが重要
マウスピースはお子さまが自分で管理するにはまだ難しい場合が多いため、保護者の方のサポートが欠かせません。装置の取り扱い・清掃・トレーニングの声かけなど、日々のフォローが治療の成果に直結します。
毎日のトレーニングの継続が必要
特にマイオブレースなどの筋機能矯正では、正しい舌の位置や呼吸・飲み込みの癖を改善するための「MFT(口腔筋機能療法)」を毎日続ける必要があります。楽しく続けられるよう、当院でも丁寧にサポートしています。
お子さまのマウスピース矯正を成功させるためのポイント
マウスピース矯正は、毎日の装着やトレーニングをしっかり継続することで効果が出る治療です。お子さま自身の努力だけでなく、ご家族のサポートや生活習慣の見直しも重要になります。
装着の習慣づけをする
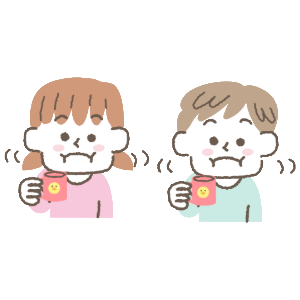 マウスピース矯正では、装着時間をきちんと守ることが治療の効果を左右します。しかし小さなお子さまにとって、長時間の装着を毎日続けるのは簡単ではありません。
マウスピース矯正では、装着時間をきちんと守ることが治療の効果を左右します。しかし小さなお子さまにとって、長時間の装着を毎日続けるのは簡単ではありません。
ご家族がサポートしながら、お子さまの性格や生活スタイルに合わせて無理なく日常生活の中に取り入れていく工夫が大切です。
たとえば、「朝起きたら装着する」「食後は歯を磨いたあとすぐ装着する」「寝る前に忘れず確認する」など、毎日の流れの中に自然に組み込むことで習慣化しやすくなります。また、装着の記録をつけたり、装着できた日に小さなごほうびを用意したり、お子さまが楽しみながら取り組める環境を整えることも効果的です。
正しい取り扱いと衛生管理を徹底する
マウスピースは、精密な歯科治療用装置です。不適切な扱いや不衛生な管理が続くと、破損や変形を招くだけでなく、汚れや細菌の付着によってお口のトラブルにつながるおそれもあります。
小児矯正の場合は、お子さまだけで管理するのが難しいことも多いため、ご家族が一緒に使い方やお手入れ方法を確認することが大切です。
基本的には、食事や間食の際にはマウスピースを外し、専用ケースに入れて保管してください。使用後は、1日1回は流水でやさしく洗い、週に数回は専用の洗浄剤を使って清潔に保ちましょう。ただし、熱湯やアルコールでの消毒は、装置の変形や劣化を引き起こす可能性があるため避けてください。
こうした取り扱いをお子さま自身がきちんと理解し、日々の生活の中で無理なく実践できるようになると、より安全かつ効果的に矯正治療を進めていくことができます。
成長に合わせて定期的にチェックする
 お子さまの口腔内は、成長とともに日々変化していきます。そのため歯や顎の発育に合わせて、矯正装置の状態や治療方針も適切に調整することが大切です。治療中は月に1回程度を目安に歯科医院にて定期的なチェックを受けるようにしましょう
お子さまの口腔内は、成長とともに日々変化していきます。そのため歯や顎の発育に合わせて、矯正装置の状態や治療方針も適切に調整することが大切です。治療中は月に1回程度を目安に歯科医院にて定期的なチェックを受けるようにしましょう
定期的にマウスピースの装着状況や歯の動き、顎の発育の具合などを確認し、必要に応じて装置の交換や治療計画の調整などを行います。成長に合っていない状態のまま治療を続けてしまうと、きちんと効果が得られないだけでなく、かみ合わせや骨のバランスに悪影響を及ぼすおそれもあります。
成長期のお子さまの小さな変化も見逃すことなく、こまめに対応していくことが治療の成功につながります。
食習慣や姿勢・日常の癖の改善が大切
マウスピース矯正では装置の装着だけでなく、日々の生活習慣の改善も治療の成果に大きく関わってきます。
食事の際によく噛む習慣を身につけることは、顎の発育や噛む力のバランスを整えるためにとても重要です。柔らかいものばかり食べるのではなく、噛みごたえのある硬すぎない食材を意識的に取り入れるように心がけましょう。
また、普段の姿勢も顎の成長や歯並びに影響を与えることがあります。特に、猫背や頬杖・うつ伏せ寝などの習慣は顎にかかる力が偏り、バランスを悪くするため注意が必要です。口呼吸や舌で歯を押すような癖(舌癖)も歯並びを乱す原因になることがあります。
このような日常の癖や生活習慣についても、歯科医師と一緒に適宜改善していくことで治療効果をより高めることができます。
保護者の方の積極的なサポートが重要
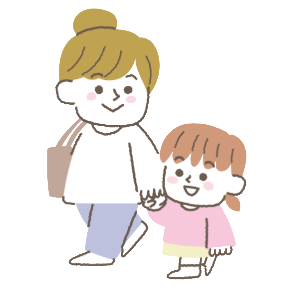 お子さまの矯正治療においては、保護者の方の積極的なサポートは必要不可欠です。装置の装着や管理を見守るだけでなく、治療に対するお子さまのモチベーションを維持することも大切です。
お子さまの矯正治療においては、保護者の方の積極的なサポートは必要不可欠です。装置の装着や管理を見守るだけでなく、治療に対するお子さまのモチベーションを維持することも大切です。
たとえば、「今日もしっかり装着できたね、よく頑張ったね」「我慢できてえらいね」といった日々の励ましは、お子さまに自信と安心感を与え、治療を前向きに続けるための精神的支えになります。